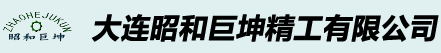大连昭和巨坤精工有限公司
メール : zhjk@jukungroup.com
住 所 : 大連开発区鉄山東路129号
〒 : 116600
T E L : 86-411-39263312
F A X : 86-411-39268817
日産自動車株式会社
たなべ?かずゆき●横浜工場 工務部 生産課。2008年入社。金沢大学教育学部学校教員養成課程卒業。当初は教職を目指していたが、「民間企業で、より広い世界に可能性を見いだしたい」と考える。形ある商品を扱う仕事がしたいと考え、製造業を目指すことに。現社の部門別採用における「生産管理部門」は、販売計画と連動した生産を行うよう製造現場と本社の要求を調整する部門であり、文系出身の自分にもチャンスがあると考えて志望。先輩社員から「若手でも仕事の裁量権が大きい」と聞いたことや、海外工場をいくつも立ち上げている点にも魅力を感じた。
■ エンジン部品の生産計画を担当。予定通りの進行が難しい中、関係部署を取りまとめることに四苦八苦
「モノづくりに携わり、形ある商品を扱う仕事でやりがいを感じたい」と考えた田辺さん。文系出身だが、現社の部門別採用にて生産管理の仕事に携わる。約1カ月の新人研修を受けたのち、横浜工場に配属され、エンジン部品の生産計画を担当することに。
「僕が担当したのは、シリンダーブロックやクランクシャフトなど、エンジンの中で核となる部品でした。『月々どの車を何台製造する』という生産計画があるので、それに従い、必要な部品数を過不足なくタイムリーに供給するための3カ月計画を立てます。工場のラインごとに生産能力は違うので、1日にどの車種を何台作れるのか、何時間生産するのか、日曜や祝日も稼働させるのかなどを考え合わせたうえで、3カ月分の生産計画と生産体制を検討。生産を行うために何人くらいの工数が必要かも踏まえ、現場を担当する製造部門に可能かどうかを打診し、生産計画と生産体制を確定させます」
また、技術部門による工場の設備工事や、設備保全部門による設備の修理?点検、品質保証部門による試作品のチェックなど、さまざまな部署で行う各種イベントで一部のラインを動かせなかったり、人手がもっと必要になることも多々あるため、関係部門の計画も織り込みながら生産計画を考えねばならない。
「生産管理は、工場における全体のまとめ役と言えます。各部門から話を聞き、納期までに必要な台数を生産できるように調整しなければなりません。配属当初は、OJT形式で先輩の仕事を見ながら学びましたが、専門用語や日産独自の用語(例:中期経営計画→『MTP』、3カ月間の発注計画→『3発』)の意味がまったくわからず、困りました。毎朝、全部門の担当者が情報共有する会議に参加していましたが、知らない言葉ばかり。少しでも早く理解するために、周囲の先輩に聞いたり、製造の現場に出向いて自分の目で確かめながらイメージをつかむ努力を続けました」
右も左もわからない状態の田辺さんだったが、配属当初からエンジン加工を手がける5ラインの生産計画を担当。もちろん先輩のフォローはあったが、自分が立てた計画に間違いがあれば、エンジン組み立てなど後の工程もストップしてしまうため、大きなプレッシャーを感じていたという。
「生産計画は“正しくて当然”なので、少しでも計画を誤れば関係各所からクレームがきます。しかし、精密部品を作る機械は非常に繊細なため、日々、オーバーヒートや故障などのトラブルが発生するもの。学生時代は『生産計画は一度出せば、その通りに進むもの』と思っていましたが、実際は計画通りにいくことなど滅多になく、トラブルに振り回されながら調整を続ける毎日でした。担当ラインで生産の遅れが出るたびに後の工程に納期調整をお願いしたり、設備の修理日程を変更してもらっていました。現場からの『こんなスケジュールでは無理』『人手が足りない』などの不満も一身に受け、板挟み状態の中で『生産に遅れさえ出なければ済む話なのに、なぜ自分がこんなことをしなくちゃならないのか』と思っていましたね」
そんな田辺さんに変化が訪れたのは、配属から2カ月後のこと。全社共通で実施する1カ月間の現場実習に参加し、身をもってモノづくりの苦労を学んだのだ。
「自分が担当しているラインに配属され、実際に作業工程に携わったことで、生産計画そのものに誤りがあると現場がどう困るのかをリアルに実感できました。変更があるたびに、どの車種のどの部品を、いつごろから作ればいいのかという優先順位が変わり、現場は混乱してしまう。自分の仕事がどう影響するのかを身をもって知ったことで、『皆さんに迷惑をかけないよう、もっと頑張ろう』と思うようになりましたね」
決意も新たに現場に戻った田辺さんだったが、その矢先、リーマン?ショックが訪れる。世の中の景気が悪化し、自動車の受注台数も大幅に減ったため、田辺さんが担当していた部品の生産数も人手も減らさねばならない状況となったのだ。
「1カ月に1万台分を5人の作業者で作っていたものが、半分の5000台分にまで減産することになりました。当然、1人当たりの生産性は悪化するので、労務費(製造原価のうち労働力によって消費する原価)を赤字にしないために人手を減らさなければなりませんが、その一方、最低限必要な人数を配置しなくてはラインが動かせないという現場の状況が。その上、当時は毎月のように減産が続いていたので、数カ月先の見通しも含めて生産計画を立てねばならない難しさもありました。会社の方針に基づいた生産計画と、現場との間で板挟みになり、苦しみましたね。結局、自分一人の力では現場を説得できなくて、上司に指示を仰いでは『上司がこう言っている』と現場に伝え、今度は『その人数では無理だ』という現場の声を上司に伝えることを繰り返すだけの状態でした。伝書鳩(でんしょばと)のように行ったり来たりするばかりの日々に悶々(もんもん)とし続けてましたよ」
システムのベンダー(提供)会社と打ち合わせ。新システム導入時のテストに当たり、処理を行う日程など、スケジュールについて話し合う。
■ 「正しいゴールを示し、周囲を巻き込む」スタイルを確立。海外工場で教育研修も手がけ、大きく成長
苦戦を続ける田辺さんだが、それまで指導してくれていた先輩社員が異動することになり、さらに苦しい状況が訪れる。人手が減り、周囲のサポートが減る一方、担当するライン数は8ラインに増え、業務量は増えていくばかりだった。
「とにかく目の前のことをこなすためにがむしゃらに頑張り、試行錯誤を続けました。しかし、自分の中で『こうしたい』という明確なビジョンが持てなかったため、全部門の担当者が集まる毎朝の会議でも方針が決められず、各部門が言いたいことを主張し合う状態。全体をまとめて引っ張ることができず、成果を出せないどころか方針決定が遅れたことで労務費などのロスも発生してしまい、ストレスは溜まる一方でした」
それからさらに9カ月後、リーマン?ショックによる影響が底を打ち、景気がV字回復に向かう中、生産計画も一気に増産傾向に切り替わる。しかし、急な変化にラインの生産能力がついていけず、計画通りの生産数を満たせない状況に陥る。
「人手を減らしていましたし、それまで眠らせていた設備の修理や点検も追いつかず、後の工程に計画通りの部品数を渡せない事態が発生。必死で調整を続けていたにもかかわらず、製造部門から『今月は生産計画通りに進めることは無理』と言われたんです。前月に計画に対してOKをもらっていたので、『今さらひっくり返されても困る』と強く主張したところ、険悪なムードになり対立することに。自分としては、全体がうまく回るよう必死で頑張ってきたつもりだったので、『一体、何のために仕事しているんだろう』というむなしさを感じました」
この状況を見かねた上司の配慮で、田辺さんは一時的にライン担当を外れ、在庫削減の特命業務に就くことに。
「在庫削減とは、生産ラインにおけるロスや課題を分析し、改善によって在庫数を適正化?削減する業務。在庫削減という目標を達成するため、一つひとつの課題を解決していく仕事なので、まず『ゴール』のイメージを描き、そのためにやるべきことを考えていきました。こうした手順を学ぶうちに、最初に自分が『こうあるべきだ』という目指す方向性を示すこと、そして、周囲の人のマインドをそこに一致させていくことが大事なのだと気づくことができましたね」
2カ月後、再びライン担当に復帰した田辺さんは、「正しいゴールのあり方=お客さまの要求を満たすこと」を常に思い描くよう心がけていく。部門担当者との会議で反対意見が出ても「お客さまに製品を届けるためにも、一緒に頑張りましょう」と伝え、一つひとつの課題解決に向けて全体を導いていった。
「みんなでディスカッションしながらゴールに向かって一丸となることができました。周囲を巻き込み、全体をまとめるやりがいを感じると同時に、『どんなに難しい局面が訪れても、そこでつまずいたら皆に申し訳が立たない』という強い責任感が芽生えましたね。気づけば、復帰の2カ月後には、自分一人でエンジン加工の全ライン、17ラインを回せるまでに成長。また、このころから、困難な状況こそ、周囲との連携を深め、知識や経験を積んで成長できるチャンスでもあると気づき、『どんなトラブルも楽しもう』が自分のキャッチフレーズになりました(笑)」
この後、田辺さんは電気自動車用モーターの組み立て計画部署に異動し、生産計画を担当。海外工場のメンバーに向けた教育?指導も経験する。
「インドの工場が生産計画を作るシステムについて指導してくれる人間を探していると上司から聞き、迷わず立候補しました。現地では、最初は一つひとつの機能について指導していきましたが、皆次第に飽きてしまい、やがて研修をボイコットされてしまったんです。理由を聞くと、『業務の中でどう使うのか、どう生かせるのか、もっと実践的なことを教えてほしい』と言われました。教科書通りの指導ではダメだと感じ、アウトプットが見えるようなシミュレーションやケーススタディを教えることに。その結果、皆高いモチベーションで参加してくれるようになり、みんなが頼ってくれるまでになったんです。システムの詳しい内容に関しても聞かれるので、僕自身もおおいに勉強させられました。また、この後、ブラジルの新工場立ち上げの教育研修も担当しましたが、インドでの経験はもちろん、これまで生産計画で学んだことをすべて生かし、“正しいゴールを思い描かせながらトラブルシューティングをしていく”という実践的な研修を行うことができました。自分にとっての集大成とも言える内容に大きな達成感を得て、ひと回り成長できたと感じます」
現在、田辺さんはシステム企画を手がける部署に異動し、生産計画のシステムにおける機能の追加や改修などを手がけている。
「自分自身が現場や、海外の研修で経験したことを生かし、生産管理に携わるシステムのユーザーにとって使い勝手のいいものを作るように心がけています。この仕事で一番やりがいを感じるのは、人に感謝され、『ありがとう』という言葉をもらう瞬間です。生産管理でも、教育研修でも、最後はみんなが『ありがとう』と言ってくれると、すごくうれしい。その言葉を聞くと、自分の努力が報われるような喜びを感じますね。今後は、生産管理のみならず、さまざまなジャンルでも指導や改善に携わり、多くの人の手助けになるようなことをしていきたいと思います」
ベンダー会社との打ち合わせに向けて資料を作成。新たに導入するシステムについて、どんな機能をつけるかなどの要件をまとめる。
■ 田辺さんのキャリアステップ
STEP1 2008年4月 研修時代(入社1年目)
入社後、1カ月間の新人研修を受ける。最初の10日間は、同期約200名と一緒に会社全体の概要や各部門が手がける業務に関する基礎研修を受ける。また、各工場を見学し、現場の仕事風景を間近に見る機会も。その後、配属先部門での部門別研修に参加し、生産の流れなどを座学で学ぶ。「部門別採用だったので、入社時に生産管理に携わることは決まっていました。座学を通して具体的にどんな仕事をするかが見えたし、それまで知識のみで知っていた生産管理について、実際にどんな運営がされているのかがわかって、すごくワクワクしました!」
STEP2 2008年5月 横浜工場工務部生産課時代(入社1年目)
エンジン部品(シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、コンロッド)の生産計画を担当。現場のやりとりを知るために会議にもどんどん参加したが、文系出身で工学系の専門用語に詳しくないうえ、日産独自の用語を理解できずに混乱する日々。配属直後から先輩のフォローを受けながら生産計画を作っていったが、設備故障の多さに愕然(がくぜん)。挽回(ばんかい)生産のためにラインを動かすことを優先し、機械の点検や整備のスケジュールを後にずらす調整をした結果、逆に故障トラブルが発生して間に合わなくなるケースも。しかし、生産が遅れれば、後ろの工程を手がけるエンジン組み立てラインや海外工場に必要な部品を届けられない状況になるため、板挟みの状況を味わった。
STEP3 2012年 横浜工場 組み立て計画担当時代(入社5年目)
電気自動車用モーターの組み立てラインにおける生産計画を担当。仕事内容は前部署とほぼ同じだが、現場をスムーズに動かすため、その日のタスクが確認できる新たなエクセルのツールを自ら作成。「今ある在庫数を基に、現時点で何日先まで要求された生産数を満たすことができるかなど、全体の進捗状況をグラフで描くツールを作成。これのおかげで『いつまでにどれだけの数を作らねばならないのか』を把握することができるようになり、現場を担う製造部門の意識を高めることができました。現場の監督者からも『自分たちで作成できるようになりたいから、作り方を教えてほしい』と言ってもらうことができ、強い現場づくりに役立つことができたと感じました」。
STEP4 2012年 海外研修指導担当時代(入社5年目)
自ら手を挙げ、インド工場の社員4名と現地スタッフ30名に向けた生産管理システムの教育研修を手がけることに。英語は日常会話程度しかできなかったため、3カ月間かけてしっかりと準備を進めた。「自分でシステムについて勉強し直してから、ポイントとなる部分を英語に訳し、用語集も作っていきました。しかし、現地で教科書通りの指導では彼らにとって意味がないと知って、そこからは身振り手振りを交え、絵やグラフを描いたりしながら意思疎通を図っていったんです。教える側にとって、教えられる人はお客さまでもあります。彼らがどういう姿を目指しているのかを知らないまま、一方的に押しつけの教育をしてもダメだということを学びました。現地のメンバーに『ありがとう。あなたは私の先生です』と言ってもらえたことがすごくうれしかったですね。これまでのさまざまな経験は、常にユーザー目線を考えなくてはならない現在のシステム企画の仕事にすべて生きていると感じます」。
■ ある日のスケジュール
9:00 出社。メールチェック。海外拠点からの問い合わせなど、緊急性の高そうなものから対応する。
10:00 システム企画部のグループメンバーと次世代生産計画システムの基本構想について打ち合わせ。
11:30 中国の新工場メンバーと朝の定例電話会議。システム導入の準備?テストを進めているため、前日までの進捗と課題を確認。
12:00 ランチタイム。同僚と一緒に自作した弁当を食堂で食べる。
13:00 翌月に来日予定のメキシコ工場メンバーを対象に行う教育研修の日程や内容について、グループメンバーとすり合わせ。
15:30 タイ工場のメンバーと電話会議。年末のシステムアップデートに向け、業務への影響度を測る現状調査の内容を共有。
17:00 中国の新工場メンバーと夕方の定例会議。当日の進捗と今後の課題を確認。
18:00 翌日の予定を確認した後、退社。
■ プライベート
2014年初めごろから自炊をスタート。毎日の弁当作りはもちろん、ポトフや角煮、ラタトゥイユなど、作ってみたい料理に挑戦している。「手際良く進める手順や段取りを考えながら作るのが楽しいですね!」
大学時代からアーチェリーを続け、今でも職場近くの練習場に週に一度は通っている。「かなり筋力を使うスポーツなので、筋トレも続けています。集中する時間が、いいリフレッシュになっています」。
革靴のコレクションも趣味のひとつ。10足以上集め、それらを手入れすること自体が大好きだそう。「いろんな種類の革靴を集めています。毎週日曜日にしっかりと磨き上げ、自分自身に気合いを入れています(笑)」。