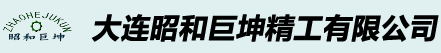大连昭和巨坤精工有限公司
メール : zhjk@jukungroup.com
住 所 : 大連开発区鉄山東路129号
〒 : 116600
T E L : 86-411-39263312
F A X : 86-411-39268817
イノベーションは、事前に要件定義できない
イノベーションの歴史を考える上で、日本を代表する企業の1社であるトヨタ自動車は、大いに参考になります。同社は、もはや世界的な巨大企業ですが、今でも様々な新しい技術を開発し、社会に大きな変化を与えており、ハイブリッド車などは、まさに、全世界の自動車産業に影響を与えるだけでなく、環境問題やエネルギー問題にも大きく貢献しています。
2014年3月に放送されたトヨタの創業者を描いたTBSの2夜連続ドラマ「LEADERS リーダーズ」は、国産自動車を生みだすまでの物語が描かれていました。何度も失敗を繰り返し、資金不足で苦しむ中で、最後には開発・量産化に成功した、というのがあらすじです。
あのドラマの中でもう一つ興味深いことに気づきました。トヨタは最初に目標を「小型大衆車」に据えていたことです。明確に、「小型」であって、かつ「大衆でも買える自動車」と宣言しました。
イノベーションを目指し、新しいことにチャレンジする場合、最初の発想は「小型大衆車の国産化」というようにシンプルな形にすることです。目指す方向が正しかったため、その後の「大衆化」で自動車産業の規模は一気に拡大し、関連する産業として精密機械、精密部品、ロボティックス、ローン、保険、道路建設、石油産業などが発展し、ビル建設や住宅産業にも影響を与えました。すそ野を含め自動車産業は、日本のGDP(国内総生産)のうち10%以上、50兆円以上になります。つまり巨大なバリューチェーン(価値連鎖)を築いたわけです。あの挑戦と成功が無かったら、今日の日本の基幹産業が何だったのかと思います。
新しい事業や製品は、最初から高度なものより、初期の段階はシンプルで値段も安いもので始まり、市場の要求と共に進化させ機能追加し、事業が拡大していきます。初めから将来要求される機能や品質をデザインインできるはずがないのです。
一例として、当社の事例を挙げます。創業者でCEOのマーク・ベニオフが1999年、35歳で創業するときの発想は「なぜ、企業のシステムは、アマゾンやヤフーの様に、簡単に使えないのだろうか」というものでした。
最初は、簡単なコンタクト・マネジメントという機能から始まりました。顧客ごとにカスタマイズできる設定機能もありません。これは、法人向けのサー ビスとしては致命的でした。その後、継続的な改良が加えられ、15年経った今でも年3回のペースでバージョンアップをしています。
まず必要最小限の機能を作りいち早く市場に投入。顧客の要望を聞きながら、求められている機能を付け加えていくというビジネスの進め方は、トヨタの創業期に似ているといえるでしょう。機能を追加する中で当初の企画と全く異なるものになっている場合もありますが、ある規模になった時に、初めて外部からはイノベーションと認められるようになります。
つまり、どんなに斬新であっても、アイデアだけでは、イノベーションとはいえません。シンプルなアイデアを実行に移し、実験し、多くの人の意見をも らい、改良を加えて、社会に普及した時、イノベーションと呼ばれるのです。 教訓は「小さくてもいいので、まずは真っ先にやってみる」ということでしょう。
最近の米国西海岸で成功している企業の共通点として、「Lean Start Up(リーンスタートアップ、リーンとは"削ぎ落とした"という意味)」という言葉があります。リーン生産方式と言う考えがあって、その考えを新規企業の経営に応用した話です。
『リーンスタートアップ』の著者であるエリック・リース氏が日本で講演をした時に、会場から「この考え方は日本で通用するだろうか」との質問があったそうです。その際に、著者は「リーン生産方式の原点はトヨタ生産方式です。日本が原点であり、合わないはずがない」と答えたそうです。
同じ本の中では、Agile (アジャイル:俊敏な)開発手法やアーキテクチャなどが重要なものとして紹介されています。 これもトヨタに似たような考え方があります。トヨタの重要な経営理念のひとつである「現地現物主義」です。これは、創業者の豊田喜一郎氏の言葉ですが、豊田章男社長も大事にしている言葉です。
資本の力が弱かったトヨタが世界に対抗するために、現場の工夫による製品の改良(不良品の減少)が必要だったということが背景にあります。現場での些細な問題や変化に気づき、迅速に改善を繰り返していくことをトップ自ら重視しているのです。この現地現物の理念と『リーンスタートアップ』に紹介されているアジャイルの考え方は、よく似ています。
イノベーションとは異なり、ソリューションという場合には、要件定義がまず先に必要になります。経営上の課題があって、現状分析し解決策を開発し実行するシステム開発の手法がソリューションです。多くの場合、業務効率向上やコスト削減などを目的としています。
課題が明確になっている場合、その原因を分析し、システム要件を明確にした上で、開発や導入計画を作り、工数見積もりや投資対効果を算定し実行する。これらの企画や計画は、経営全般において、非常に重要なことであるのは間違いないでしょう。
ただし、ソリューションというと、大きな構想に対して、莫大な費用が必要になる場合もあるため、最初からきちんとした構想や計画、投資対効果などの算出が必要になってきます。戦略的な課題(例えば、新規事業、新規市場などの拡大策)では、ソリューションアプローチはあまり適さないのです。
新事業や新規市場に関しては、その現状分析する事実そのものが非常に限られたており、仮説を設定して計画を策定する訳ですが、仮設に入れるパラメーターを少しでも間違えれば、シミュレーション結果は大きく狂ってしまうことになります。そんな仮説を前提としたら、投資対効果の算定は非常に難しいか、根拠の無いものと言えるでしょう。
要約すると、イノベーションは、戦略的な課題への挑戦であり、現時点で見えていないものへの着手です。ソリューションは、明確になっている現状の課題に対して、システム化の要件定義を行うもので、効率化や改善が目的になります。
私が過去に携わった顧客企業を振り返ると、戦略的な課題であるにもかかわらず、それをソリューションとして実現しようとして、どうしても上手くいかない場合がありました。こうしたものは、何度やっても成功しないプロジェクトになりがちで、過去に、CRM(顧客管理システム)などの分野に多くみられました。外部のシステム開発者は要件定義できないものを、無理に要件定義しようとするため多くの時間とコストを費やし、複雑で高度なシステムを開発することになります。結果、誰も使わないシステムになってしまうのです。
まして、自社の販売戦略や商品戦略などは、まさに戦略でありイノベーションの領域。そこを外部に求めるというのは、愚の骨頂ではないでしょうか。私が経験した、成功したプロジェクトの多くは、ユーザー企業自身が基本的な設計を考えて、必要に応じて俊敏に改良を加えていったものです。